他責思考の人間は、割と人生詰んでいると思っています。
それはなぜかというと、負の無限ループに囚われてしまっているからです。
今回はそんな他責思考の負の無限ループについて考えてみました。
目次
①そもそも未熟だから他責思考になる
②反省しないから未熟なまま
③負の無限ループから抜け出すには?
④良い歳で他責のやつは化け物だから、覚悟が入ります
⑤でも過剰な自責も良くない
①そもそも未熟だから他責思考になる
他責思考の人間はそもそも未熟です。
そのため、ストレスを受け止めることができません。
(まともにストレスを受け止めると、未熟な心が壊れてしまう)
ゆえに、ストレスが発生する事態(仕事に失敗した、自分が間違えていた、など)が生じた場合、他人や環境を責めることでストレスを手放すわけです(自分は悪くない → ストレスフリー)。
これが他責思考の発生メカニズムだと思います。
【補足】ストレスの処理の仕方
通常の人間はストレスを受けた際に、それをきちんと受け止めて、反省として昇華させます(成長する)。
しかし、未熟な人間はストレスを受け止められないので、以下のような方法でストレスを手放します。
・他責 … 自分以外のものが原因だと責める → これが一番多い気がします
・否認 … 自分はそんなこと言っていない、やっていないと事実を否定する
・退行 … 泣きじゃくったり、無視したり、子どものようふるまう など
②反省しないから未熟なまま
人は反省するから成長することができます。
何かを失敗した、自分が間違っていた、という状態は自分にとってストレスですが、そのストレスが人を成長させます。
→ 失敗したときのストレスを脳は覚えていて、同じようなストレスを感じないように気を付けよう、というのが成長だと思っています(傷ついた分だけ成長する)。
しかし、他責思考の人間は、自分のせいではないと考えて、そもそもストレスを感じないようにします。
それゆえに、成長することができません。
そのため、他責思考の人間では負の無限ループが起こります。
(そもそも未熟だから他責思考になる ⇔ 他責思考で反省しないから未熟なまま)
③負の無限ループから抜け出すには?
他責思考の負の無限ループに入ってしまうと、一生未熟なままで人生が終わってしまいます。
では、この無限ループから抜け出すには、どうすれば良いのでしょうか?
基本的には2つのパターンがあると思います。
1)本人が気づく
2)他人が気づかせる
1)本人が気づく
人生には色々なことがあるので、何かのきっかけで自責思考に目覚めることもあり得ると思います。
(キーパーソンとの出会いとか、たまたま何か良い成功体験をするとか)
他責思考の人間が近くにいる場合は、偶然、自責思考に目覚めるのを祈る、というのも手だと思います。
2)他人が気づかせる
もう一つの方法は、誰かが「あなたは他責思考だよ」ということを教えて、教育してあげることです。
例えば、子どもは未熟なものなので他責思考になることもありますが、きちんと教育することで自責思考になっていくと思います。
「私悪くないもん!」という子どもでも、きちんと教えていけば「私が悪かったな」と思えるようになっていくはずです。
・こういう悪いことをしたから、怒られたんだよ
・こういう良いことをしたから、褒められたんだよ
・きちんと勉強したから、いい点が取れたんだよ
というフィードバックを与えることで、良いことも自分の責任、悪いことも自分の責任、という思考が育っていくと思います。
このように、きちんとした教育をすることで、他責思考を身につけさせることもできると思います。
④良い歳で他責のやつは化け物だから、覚悟が入ります
自分の子どもの場合は親の責務として教育するモチベーションがあると思いますが、赤の他人の場合は結構大変です。
特に、良い歳して他責のやつは化け物なので、教育するには相当な覚悟が必要です。
良い歳して他責の人間は、いわば借金の塊です。
親や先生が教育をしてこなかった、あるいは教育を諦めた、ということが積み重なった状態であり、子どもの頃に学ぶべきことを積み残したまま大人になった人間です(借金の塊、やってこなかった宿題の山)。
こういう人間を自責思考に教育するためには、今まで親や先生が教えてこなかった社会常識などを、あなたが代わりに教えてあげる必要があります。
つまり、あなたがその人の親や先生の代わりに、教育面の借金を返してあげるのです。
しかしながら、こういう借金を返すためには、たくさんの時間や大きな手間がかかります。
なので、他責思考の人間の借金を返すためには、あなたが自分の時間や手間を差し出す必要があります。
このように他責思考の大人を教育するには相当な覚悟が入ります。
⑤でも過剰な自責も良くない
最後に、自責思考になるのは良いのですが、過剰に自責になるのは良くないという話もします。
子どもを例にして考えると、他責でも問題がありますし、過剰な自責も問題があるのが分かるかと思います。
他責 … 私悪くないもん!
過剰な自責 … お父さんとお母さんが離婚したのは、ぼくのせいだ
この場合、はたから見ると、お父さんとお母さんが離婚したのは当人同士の問題で、子どもには責任がないのが分かると思います。
しかし、過剰な自責をしてしまうと、自分がコントロールできること以外にも責任を感じてしまって、余計な苦しい思いをしてしまいます。
ということで、他責にするのはダメですが、過剰に自責になるのもダメです。
どう考えても自分にはコントロール権がなかったなー、という出来事については、自責しないことも大切です(運が悪かったわ!と思うのも大切)。
そのバランスがまた難しいのですが。
以上、他責思考の負の無限ループについて、考えたことでした。
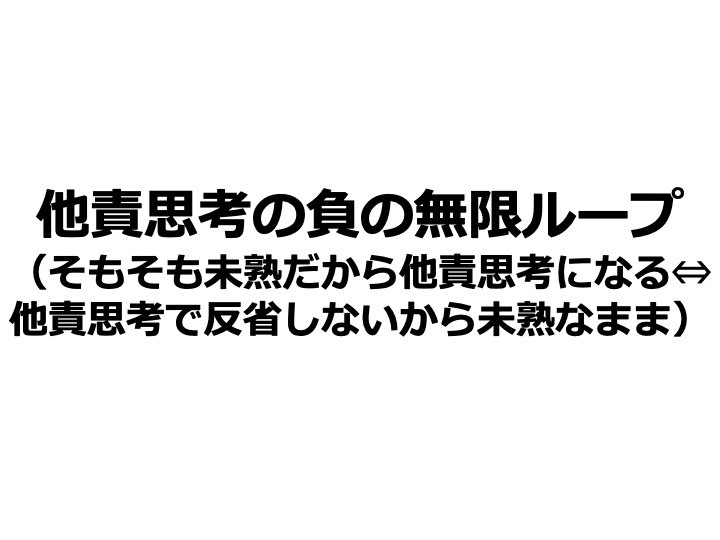
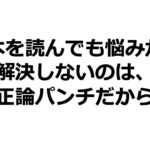
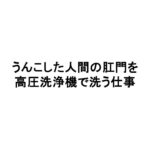
コメント